わが国は豊かさを感じにくい国となるのか ~高齢化と労働市場の構造変化が示唆するもの
2015.03.02国民一人当たり実質経済成長率はG7諸国平均並み
わが国の国民一人当たり実質成長率は、2000年以降、G7諸国平均並みの伸びを続けている。2008~09年のリーマンショックによる落ち込みも、2013年までに取り戻した。国民生活は着実に豊かになってきたといってよいだろう。
それにもかかわらず、多くの認識は「国民生活はほとんど改善していない」というものではないか。なぜ、そうなるのか。ここでは労働市場の構造変化を踏まえて、一つの仮説を考えてみたい。
女性の労働市場参加増が300万人の就業人口減をくいとどめた
最近の労働市場の構造変化は劇的だ。団塊世代が労働市場から大量に退出する一方で、女性がこれを急速に代替している。
労働市場に関しては、従来、いくつかの特徴が指摘されてきた。一つは、労働力人口比率が60歳を過ぎると急激に低下することだ(注1)。男性の労働力人口比率をみると、50代まで90%台半ばが維持されたあと、60代は60%台まで低下している。
(注1)労働力人口比率とは、「働いている者」および「働く意思があり、かつ求職活動を行っている者」の総人口に対する比率
もう一つの特徴は、女性の労働力人口比率が30代および40代前半にいったん低下することだ。すなわち、出産、子育て期に職場を離れる女性が多い。この結果、女性の年齢別労働力人口比率のグラフは、中ほどにくぼみが生じる形状――いわゆる「M字カーブ」――となる(参考1)。
(参考1)男女別年齢別労働力人口比率
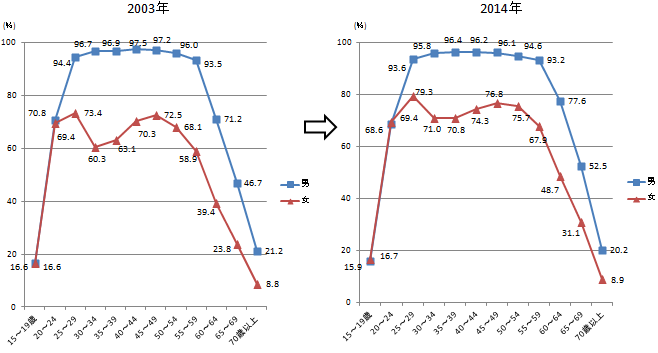 出典:総務省「労働力調査」を基にNTTデータ経営研究所が作成
出典:総務省「労働力調査」を基にNTTデータ経営研究所が作成
仮に、このような特徴が現在まで維持されていたならば、わが国における労働供給は、2000年代後半から大幅に減少していたはずだ。団塊世代が60歳を超え、労働市場からの退出期を迎えたからである。
その度合いを2003年時点の就業率を基に試算すると、2014年までの11年間で国内就業者数は325万人減少していたはずとの計算結果となった。これは2003年時点の全就業者数の5%強にあたる(参考2)。
しかし、実際の就業者数は11年間でむしろ39万人増加した。上記試算結果に比べれば、364 万人の上振れである。その理由は、(1)女性全体の就業率向上と、(2)60~64歳男性の就業率向上にあるが、要因分解すれば前者の寄与が8割強を占める。
つまり、女性が団塊世代の労働力を代替することで、労働供給の縮小は食いとどめられた。この結果、女性の「M字カーブ」も急速に解消に向かっている(注2)。
(注2)なお、女性とは対照的に15~59歳男性の労働力人口比率は、2003年から2014年にかけて各層とも低下している(2014年8月「若者世代の労働参加はなぜ男女で対照的な動きなのか」参照)。
(参考2)高齢化に伴う就業人口の変化試算と実績(2003年→14年)
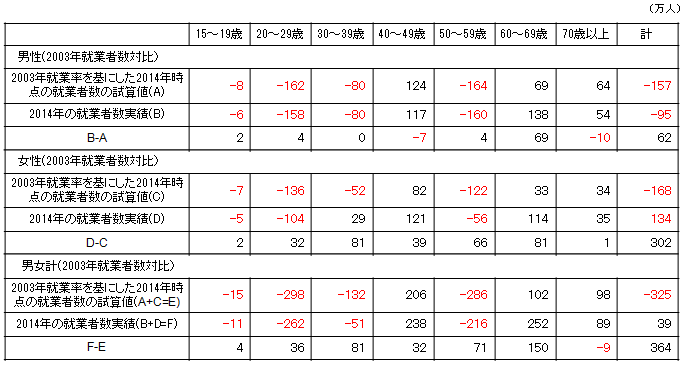
(注)試算値は、2014年時点の年齢別人口に2003年時点の年齢別就業率を乗じ、2003年時点の就業者数実績と比較したもの。
出典:「住民基本台帳人口移動報告」(総務省統計局)を基にNTTデータ経営研究所が作成。
労働市場の構造変化がもたらす実体経済へのインパクト
このように女性の労働市場参加が増えたことは、わが国経済に好ましい影響を与えてきた。もし、こうした追加的な労働力の供給がなければ、わが国の成長率は大幅な低下を余儀なくされたことだろう。
ただ、女性の労働市場参加が、――絶対数はほぼ同数にしても――、団塊世代の労働力とは技能・得意分野や環境面に違いがあることに注意が必要だ。
第1に、30代ないし40代前半女性の労働市場復帰は、子育ての関係からどうしても時間面の制約を受けやすいのが現実だろう。第2に、女性の就業分野は、どうしても介護や、保育などのサービス部門が中心となる。そうであれば、製造業や建設業などの人手不足はなかなか解消されにくい。企業の総人件費はこれまで団塊世代の退職により圧縮されてきたが、今後は人手不足に伴う賃金の上昇により押し上げられていく可能性が高い。
高齢者が豊かさを実感することのむずかしさ
では、こうした労働供給の劇的なシフトは、国民の平均的な生活実感にどのような影響を及ぼすだろうか。
まず忘れてならないのは、家庭内での家事や子育ても生産活動であることに変わりがないということだ。たしかに、GDPの計算上は、家庭内での労働は生産活動として認識されない。しかし、これは統計上の問題にすぎない。
このことは、家庭内の女性が自宅で保育園を立ち上げ、たまたま自分の子供だけを預かった場合を想定してみると、わかりやすい。家庭内での活動と違い、この場合はGDP統計上生産活動として計上されるが、両者に本質的な違いはない。
したがって、女性の職場復帰は、当該女性にとっては労働投入量の限界的な増加を意味する。費用逓増の法則にしたがえば、限界的な労働コストの逓増だ。そうであれば、限界的な労働コストの逓増に見合った所得が得られるかどうかが、生活実感としての豊かさを決める一つの鍵となろう。
一方、退職後の高齢者は、対照的に限界的な労働コストが逓減していく。高齢者にとっての労働は自らの生活を支える家事や孫の世話が中心となり、退職前に比べ労働投入量は減少している。
問題は、こうした労働状況に対し消費から得られる効用を高齢者がどのように感じるかである。たとえば、旅行に出かけたり、趣味を楽しむのであれば、効用は大きく、労働コスト対比でみても十分に豊かさを実感できよう。
しかし、高齢者の消費のかなりの部分は医療や介護サービスにあてられる。これらは、旅行などと違い、やむを得ず消費する性格が強く、「豊かさ」を実感しにくいようにみえる。治療や手術を受けて長生きすることは、本来、人々の満足を高めることであるが、どれほど多くの人が、そこから「満足」を感じ、「豊かさ」を実感しているだろうか。
「豊かさ」を感じにくい社会にあって
以上をまとめれば、女性は限界的な労働コストの増加を感じやすく、高齢者は医療サービス等の消費に効用を感じにくい。そうであれば、労働市場の構造変化とともに、国民の平均的な生活実感は「豊かさ」を感じにくいものとなる可能性がある。
これは、高齢化社会の宿命といえるかもしれない。それ自体は避けようがないようにみえる。しかし、そのうえでも、現役世代と高齢世代の受益と負担のバランスには配慮する必要がある。
現在の財政状況をみれば、社会保障支出の1/2近くが税と国債発行によって賄われている。これは、費用負担を現役世代や将来世代に転嫁していることにほかならない。現役世代と高齢世代の受益と負担のバランスはいかにも悪い。
やはり、一人ひとりができる限り長く働くことで、現役・将来世代の負担を軽減し、生活実感としての「豊かさ」のバランスを少しでも回復する努力が重要だろう。(2015年1月「なぜ私たちは70歳代まで働かねばならないのか」参照)。
以 上
【関連コラム】
■ 「外国人」は労働市場にどれだけ貢献しているか?(2016.06.01) ■ 若者世代の労働参加はなぜ男女で対照的な動きなのか ~~労働力率にみる労働事情(2014.08.01) ■ なぜ私たちは70歳代まで働かねばならないのか ~~社会生活から考える日本経済(2015.01.05)
