キャッシュレス、誰がコストを負担するか:山本謙三の金融経済イニシアティブ ~No free lunch、タダで利用できる幸運はない
2019.04.01
前回のコラムで、日本は、電子マネーが銀行発行のデビットカードを凌駕する唯一の国であることを書いた(2019.03.01「なぜ銀行はキャッシュレスに出遅れたか」参照)。
たしかに、電子マネーに代表される非銀行系のキャッシュレスは、利用者(消費者)にとって「お得感」が強い。ポイントもクーポンもつく。だが、キャッシュレスをめぐる費用・便益の構造は複雑だ。インプリシットな(暗黙の)負担もある。利用者は、本当にコスト負担なしに便益を享受しているのだろうか。
キャッシュレスにはコストがかかる
キャッシュレスの実現には、おおまかにいって、2つのシステムが必要となる。第1は、利用者と店舗(加盟店)間のインターフェースだ。第2は、利用者の預金口座から店舗の預金口座に資金を振り替える仕組み(決済手段)である。
最近の焦点は、もっぱらインターフェースの革新に当たる。スマホやQRコードなどの技術革新をとりこみ、利便性を高めることで利用者を増やす狙いがある。
だが、簡便な手段とはいえ、新たなインターフェースの構築には費用がかかる。資金を振り替える仕組みへの接続も必要だ。セキュリティの強化も欠かせない。このコストを誰が負担するかは、ビジネスモデルを決める重大な要素となる。
現金削減の最大の恩恵は中央銀行に
現金の削減(キャッシュレス)で、最も恩恵を受けるのは中央銀行だ。中央銀行は、印刷局に支払う銀行券の製造費用や、銀行券の鑑査、流通などの費用を削減できる(注)。
(注)ただし、中央銀行全体の収益への効果は。むしろマイナスとなる可能性がある、中央銀行は、現金(負債)の発行見合いに国債(資産)を保有し、運用益を得ている(運用益から費用を差し引いたものが、いわゆる「シニョリッジ」)。現金残高の削減は、費用を減らすと同時に、運用益を減少させる。
したがって、費用・便益を見合わせる観点からは、中央銀行自身がキャッシュレス手段を提供するのが最も分かりやすい。しかし、これには厄介な問題がある。中央銀行のキャッシュレスは、個人や企業が中央銀行に預金口座を開くのに等しい。すなわち、電子マネーでの代金決済は、日銀内部に開かれた利用者名義・店舗名義の口座間で振り替えるのと同じである。
そうであれば、例えば信用不安が生じるような場合、民間銀行の預金が中央銀行電子マネーに大量にシフトするおそれがある。信用不安の増幅を避けるには、慎重な制度設計が必要になる。現在キャッシュレスの提供が民間に限られるのは、そうした配慮からだろう。
現金削減の効果をあてにするだけでは、ビジネスが成り立たない
では、民間にとっての現金削減効果はどうか。実は、企業や個人が享受する費用削減の効果は、銀行や大型小売店を別にすれば、さほど大きくないだろう(参考参照)。
たしかに、現金には受払いに伴う煩雑さや持ち運びのリスクがある。しかし、現金はタダで保有できるうえに、日本の場合は犯罪が少なく、保有のリスクも小さい。手数料を支払ってまでキャッシュレスに移行するインセンティブは、それほど強くないとみておくべきだろう。
結局、民間事業者は、現金削減の効果をあてにするだけでは、キャッシュレスのビジネスモデルが成り立たない。費用削減効果の大半を中央銀行が享受するにもかかわらず、その損益は国とのやりとりで処理され、民間に還元されないことに大きな理由がある。
実際、従来のキャッシュレス手段であるクレジットカードや電子マネーの事業者は、費用削減以外のメリットを付加したうえで(あるいは強調しながら)、加盟店や利用者に手数料等の負担を求めてきた。
加盟店がクレジットカードを導入するのは、市場シェアの拡大を期待してのことだ。個人は、後払いのメリットやポイントの還元、リボルビングの利用を意識して、カードに加入してきた。流通業者がみずからコストを負担して電子マネーを発行するのは、顧客の囲い込みに有効と考えるからである。
(参考)キャッシュレス化(現金削減)の費用、便益
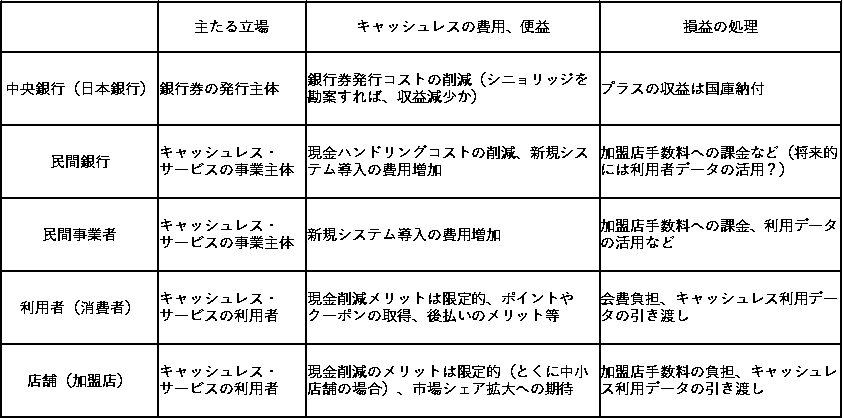
(出所)筆者作成
消費者は、利用データを見合いにキャッシュレスを利用
それでは、キャッシュレスをめぐる最近の熱狂ぶりはどう理解されるだろうか。特徴は、新規事業者が赤字覚悟のキャンペーンを行っていることだ。例えば、利用者への多額のキャッシュバックや加盟店手数料の低額据え置き(一定期間)などがみられる。
新規事業者の狙いは、キャッシュレスの提供を通じて、膨大なデータを収集することにある。ビッグデータや人工知能の時代を迎え、データの収集、解析が企業の競争力向上の鍵を握るとされてきた。
典型的には、ターゲッティング広告がある。データを集め、嗜好、消費パターンを解析することにより、利用者ごとに関心をもちそうな商品ラインアップを画面上に表示するやり方である。アマゾンやグーグルなどのプラットフォーマーがこぞって決済事業に進出するのも、同様の理由である。
こうした構図のもとでは、一義的には民間事業者がコストを負担する。しかし、実態的には、利用者がみずからの利用データを事業者に引き渡すことによって、コストを負担しているとみることができる。いわば利用データを事業者に売り渡し、対価をそのまま事業者に渡して、キャッシュレス手段を利用しているようなものだ。
個人データの引き渡しは割安か割高か
すなわち、新しいビジネスモデルは、個人データの引き渡しを見合いとするところに特徴がある。そうしたモデルは、個人データの保護が十分になされ、データ利用がルールに則ったものであれば、妥当なものだ。キャッシュレス以外の分野でも、今後、類似の仕組みが増えてくるだろう。
ただ、利用者はそうした全体像を把握しておくことが必要である。政府も、現金削減の効果ばかりでなく、個人データの収集にキャッシュレス支援の重点があることを丁寧に説明すべきだろう。政府によるポイント還元が一時的な施策であることを踏まえれば、支援は、単体で採算を計算できる「データ利用のビジネスモデル」に向けられているはずである。
問題は、利用者から得られたデータが本当に有効に活用されるかである。「データこそ宝の山」というのが共通理解だが、実際にどれほど有効に活用できるかは未知数だ。
もし、さほどの有効な使い道が見つからなければ、いつまでも赤字覚悟のサービス提供は続けられない。いずれは加盟店の手数料や利用者の会費に跳ね返ってくる。
一方、利用者や加盟店にさほどのコスト負担を求めることなく、キャッシュレスが提供され続けるとすれば、よほど割安にデータを引き渡していることを意味する。データの本来の価値はもっと高いはずだ。
この場合、新規の事業者が現れ、データ価値に見合った新たなサービスを提供してくれればよい。しかし、市場が寡占化し、割安なデータの引き渡しがいつまでも続くようならば、市場として好ましくない。これをいかに未然に防止するかが、データ市場の次の課題となる。
以 上
関連コラム
なぜ銀行はキャッシュレスに出遅れたか~電子マネーがデビットカードを凌駕する唯一の国(2019.03.01)
銀行はなぜ協業(アライアンス)に向かうのか~フィンテックを有効に活用する非金融業に、銀行はどう対抗するか(2017.01.04)
電子マネーで財布は軽くなったか?~正しい(?)電子マネーの使い道とは(2015.12.01)
銀行はなぜビジネスモデルの見直しを迫られるのか~変貌する小口決済市場(2015.08.03)
