年金受給開始年齢の選択制は、なぜ「長く働く社会」につながりにくいのか ~行動経済学が示唆する不都合な真実
2019.11.01政府の全世代型社会保障検討会議がスタートした。高齢者の就労を後押しすることが柱の一つという。
長寿化、少子化の進む日本にとって、長く働く社会づくりは不可欠だ。65歳時点の平均余命は男性19年、女性24年と、1961年に国民年金が導入されて以来それぞれ約8年、約10年も延びた。この年数程度はより長く働くこととしても、違和感はないだろう。
政府は施策の一つとして、年金受給開始年齢の選択制を、現行の「60~70歳」から「60~75歳」に拡大する案を検討している。しかし、この案に沿い実際に年金受給を高齢へ繰り下げる人は少ないだろう。なぜか。
就労期間を決める「定年年齢」と「年金支給開始年齢」
人が何歳まで働くかを決める主な要素には、健康状態、貯蓄額、定年年齢、年金支給開始年齢がある。
高齢者の働く意思を確認するため、60歳以上の労働力人口比率をみてみよう。男性の同比率は長らく低下が続いたあと、ようやく下げ止まった。長期にわたる低下傾向は、①長寿化に伴い60歳以上の人口が増えたことと②身体が動く限り働く傾向の強かった第一次産業や自営業のウェイトが低下したことが大きい(参考1参照)。
だが、低下トレンドのなかにも、1980年代後半と2000年代後半の2度にわたり、反転・上昇局面があった。前者は、60歳定年の実現に向け定年後再雇用の義務化が予定されていた時期であり、後者は65歳までの雇用確保措置が義務化された時期にあたる。
また1980年代後半には、厚生年金の支給開始年齢の本格的な引き上げも始まった。当時男性60歳、女性55歳だった同年齢は、それぞれ65歳(標準)に向けて現在も段階的な引き上げ途上にある。
すなわち、年金支給開始年齢の引き上げと定年延長の組み合わせは、人々が長く働くインセンティブとして機能してきた。今回の受給年齢選択制の拡大が長く働く社会づくりに寄与するとすれば、政府が検討を進める「70歳までの就業機会確保の義務化」とあわせて、この組み合わせと同等の効果をもつ必要がある。
(参考1) 労働力人口比率(60歳以上)の推移
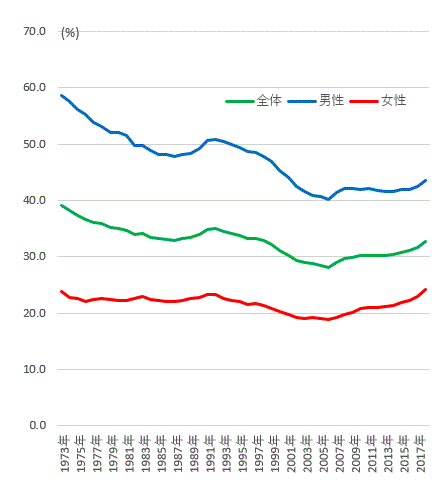
(注)労働力人口比率=労働力人口(就業者と完全失業者の計)/ 総人口。完全失業者とは、(1)仕事についていない(2)仕事があればすぐつくことができる(3)仕事を探す活動をしていた、の3つの条件を満たす者。
(出典)総務省「労働力調査」を基に筆者が作成。
繰り上げても繰り下げても「損をしない」設計
現行の受給開始年齢の選択制は、65歳を標準としつつ、60~70歳の間で受給者が開始時期を選べる制度だ。その際の受給額は、平均死亡率を基に減額、増額される。したがって、繰り上げても繰り下げても損得のない仕組みと説明されている。
たとえば、70歳に繰り下げれば、その後の受給額は標準対比42%の増額となる。また、現在検討中の75歳への繰り下げは、標準対比80数%の増額となる見込みと伝えられている。
もちろん、繰り下げ後に早く他界すれば少ない年金総額しか受け取れないが、より長生きすればより多くの総額を受け取れる。これであれば――平均死亡率が変わらない限り――繰り下げの選択が増えたとしても、社会全体の年金支給総額は変わらず、年金財政にも中立的といえる。
年金は保険か貯蓄性商品か
年金は本来長生きリスクに備えた保険であり、想定外に長生きして生活費が足りなくなるリスクに備えるものだ。受給開始の年齢を繰り下げたあと、想定以上に長生きしたときにより多くの年金を受け取れるとするのは、保険の道理にも一応かなう。
一方、長寿化の結果、日本で生まれた国民の約9割が65歳に到達しようとする時代だ。年金は、いわば受け取って当たり前の金融商品にある。こうなると、保険商品というよりも貯蓄性商品と見なされやすいのも理解できる。「長生きすれば得、早く死ねば損」と捉えるのは、保険の観念からは外れるが、やむをえないところだろう。
人は損失リスクをより大きく見積もりがち
上記のように受給開始年齢の繰り上げ、繰り下げは客観的には中立的だ。にもかかわらず、実際には、高齢に繰り下げた人の割合はこれまで1%台にとどまる。
一見、経済合理的でないようにみえるが、行動経済学の知見に基づけば大方説明がつくだろう。行動経済学は、伝統的な経済学の「合理的な経済人」の仮定に疑問を投げかけ、実験などを用いて人々が実際にどう行動するかを描写する学問だ。
その一つの知見は、「人は利益を得られる場面ではリスク回避を優先し、損失をこうむる場面では損失を極力回避する」というものだ。大胆に要約すれば、「人は得をするよりも、損をしたくない思いが強い」ということだろう。
年金でいえば、より長生きして多くの受給総額を得ること(利益)よりも、早く他界して少ない受給総額しか受け取れないこと(損失)を避けたい。リスク・リターンが同一であることが分かっていたとしても、平均的な人間は、受給繰り下げの選択を避けがちということになる。
長生きする主観的確率は高齢を想定するほど不確実性が高い
あるいは、次のような説明も可能だろう。みずからが何歳まで生きるかの確率(主観的確率)は、高齢を想定するほど不確実性が増す。
人口動態によれば、男性は60歳代前半、女性は60歳代後半から死亡率が上昇する(参考2参照)。こうした状況下では、①60歳時点で65歳の生存確率を見通すのと②65歳時点で70歳や75歳の生存確率を見通すのを比べれば、個人にとっては後者の不確実性の方が高く感じられるはずだ。より高齢での受給開始は、不確実性が高い分だけリスクが大きく見積られやすく、選択されにくいこととなる。
(参考2) 2018年簡易生命表に基づく累積死亡率
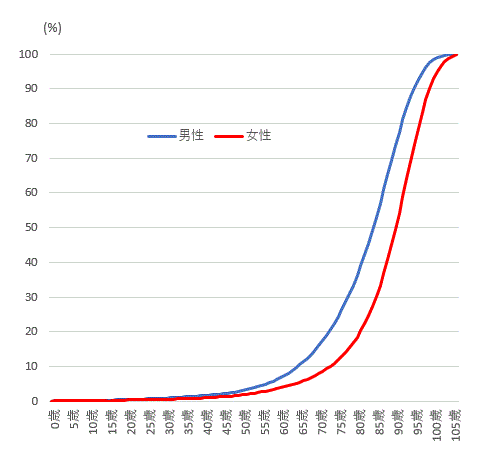 (注) 累積死亡率は「生存数」の逆数。
(注) 累積死亡率は「生存数」の逆数。
(出典)厚生労働省「平成30年簡易生命表」を基に筆者作成。
これらのバイアスを踏まえたうえで、より多くの人に繰り下げを選択してもらおうとすれば、繰り下げ時の受給額を大幅に引き上げなければならない。しかし、これでは社会全体の年金支給総額が増え、年金財政を悪化させてしまう。年金財政への中立性を維持するかぎり、この矛盾を解決するのは難しい。
支給開始年齢の引き上げも議論の俎上に
受給開始を繰り下げること自体が、不合理な選択というわけでは決してない。長く働く意思のある人にとって選択肢が増えるのは、良いことだ。制度として選択制が間違っているわけではない。
しかし、選択制の拡大が年金受給開始の繰り下げを選択する人を増やし、「長く働く社会」につながると考えるのは早計である。
原点に立ち返ることが重要だ。コトは年金だけではない。医療や介護を含む社会的費用を国債の発行で賄い続ければ、子の世代、さらに孫の世代へと、より大きなツケを順送りすることになる。将来の世代に安定した社会を引き継ぐには、一人ひとりが長く働いて税や保険料を納め、社会的費用をできるだけみずからの世代で負担することである。
現状、政府は年金受給開始年齢の選択制を強調し、支給開始年齢の引き上げ自体を検討する姿勢にはない様子だ。しかし、一人ひとりが長く働く社会を考えれば、やはり年金支給開始年齢の引き上げと定年制の廃止(または定年延長)を選択肢から外すべきではないだろう。
現在進められている厚生年金支給開始年齢の65歳(標準)への引き上げは、男性で2025年、女性で2030年に完了する予定にある。筆者の主張のように、その後も引き上げを継続するとすれば、早く決め、人々に意識して行動してもらうことが大事になる。残された時間は少ない。
以 上
[関連コラム]
なぜ私たちは70歳代まで働かねばならないのか~社会生活から考える日本経済(2015.01.05)
